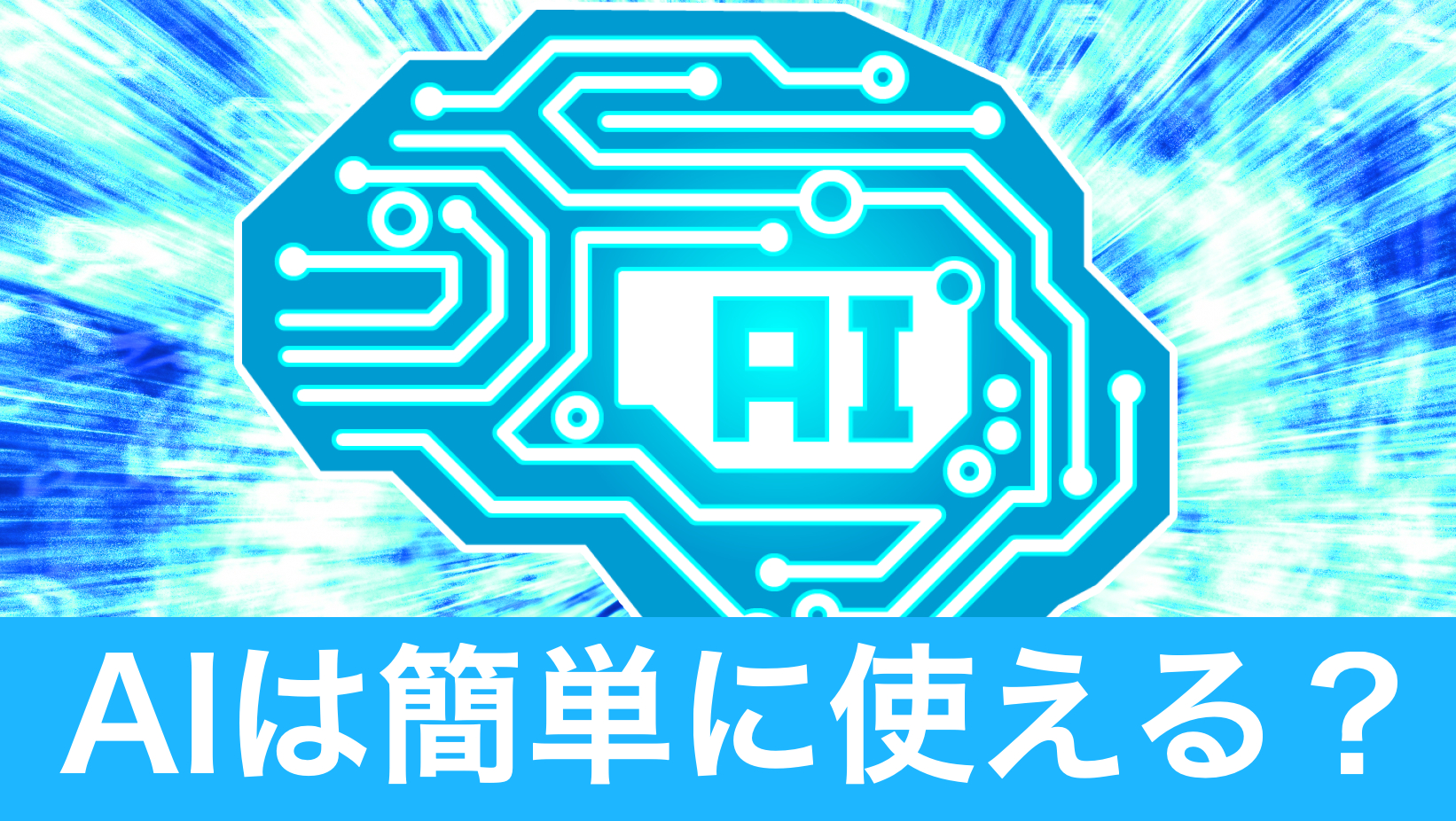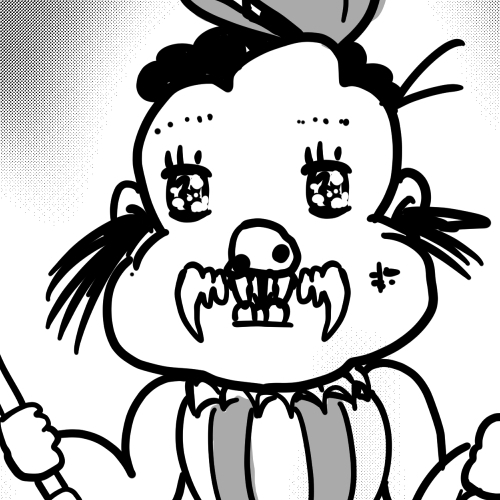どうも、ごりまつです!
近年、AI画像生成はビジネスシーンでも急速に注目を集めています。
SNSの発信や自己ブランディング、企業PRなど、多様な用途で「簡単に」「手軽に」使えるツールとして紹介されることも増えました。
ただこれは本当の意味で「簡単に使える」と言えるのでしょうか。
今回はクリエイターという視点から、AI画像生成の実態とビジネス活用について考えてみたいと思います。
誰でも簡単に画像生成できるAI
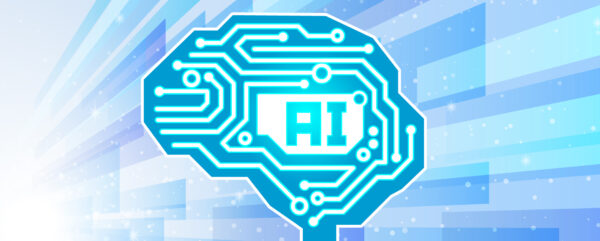
ビジネスシーンにおいてのAI画像生成は、「〇〇風の似顔絵」や「シーン指定のイラスト」の作成などが多いのかなと思います。
InstagramやFacebookなどを見ていると、ビジネス系のアカウントがプロフィール画像や投稿内で活用している方が多くいます。
たしかに、このような「サポート画像」は生成が簡単です。
指示文(プロンプト)さえ書ければ、ある程度クオリティの高い画像が出てきますからね。
ただ本当の意味で「求めている画像」を簡単に生成できるのでしょうか。
求めている画像は本当にそれ?

趣味の範囲であれば「ただただ画像を作って楽しむ」それでいいかもしれません。
しかしビジネスで使っている方にとっては「その画像が成果に結びつくか」、これが大事ですよね。
つまりAIで画像を生成すること自体が目的ではなく、その画像を用いて「どうプラスに働かせるか」が鍵になります。
これらを考慮せずに流行の「ジブリ風」「アニメ風」といったテンプレ的な画像を使っても、かえって無個性化を招き逆効果になりかねません。
皆さんもSNSを使ってて同じ画像ばかり出てくるとウンザリしてきませんか?
また実写の生成画像も「不気味の谷」のような感覚に陥るものも見かけます。
そうなるともうPRどころではなく、少し怖く感じるんですよね。
ではどうすれば効果的な画像を生成できるのでしょう。
それを考察するために、まずはAI画像生成者の立場から考えてみます。
AI画像生成者の本質は「プロデューサー」

AIを使って画像を作る人を「AIクリエイター」「AI絵師」などと呼ぶこともありますが、実際の役割に近いのは「プロデューサー」だと私は考えます。
指示を出してAIという名のクリエイターに画像を作ってもらうわけですからね。
では、そのプロデューサーとは具体的にどんなことをする存在なのでしょうか?
それは
クライアントや自分の目的に応じて
といった要素を戦略的に設計し組み立てる。
それがプロデューサーです。
ではそんなAI画像生成者がプロデューサーとして「効果的な画像」を生み出すにはどうすればいいのでしょうか。
プロデューサーには「特殊な目」が必要

プロデューサーが有効な判断を下すには、「善し悪しを見極める目」が必要です。
それはセンスではなく、「経験や学びによって培われる視点」です。
ビジネス系SNSの場合、例えばこんな目が必要になるでしょう。
他にもいろいろありますが、こういった目があると良し悪しの判断がつきます。
どの職種や業界にもそういった特殊な目ってあると思います。
私が今急に学校の先生になっても全く立ち回りが分からないと思いますし。
なので私の考えは効果的な画像が欲しければ「その道のことを学ぶ」もしくは「その道の人に依頼する」という2択。
「簡単に使える」けれど、「簡単に活かせるものではない」それがAI画像生成なのではないかと考えます。
まとめ:必要なのは「武器の使い方」

AIは非常に強力なツールです。
しかしそれを効果的に使いこなすには、訓練と理解が必要になってきます。
もちろん、「使わないほうがいい」と言いたいわけではありません。
効果も0ではないと思いますし、使っていく中で成長して魅せ方や活用方法が見えてくることもあると思います。
ただ「誰でも簡単に」というような表現には、やはり少し違和感があったんです。
なので今回は自分なりの考えを記事にまとめてみました。
この文章を読んで、
そんなふうに、何かひとつでも気づきやヒントになれば嬉しいです。
それでは!!
※なお今回は、「AI画像の善し悪し」を論じるのが目的ではありません。
あくまで画像の使い方や考え方について普段から感じていた違和感を整理し、言葉にしてみたという位置づけの記事になります。